[遺言・後見・家族信託]
成年後見 vs 家族信託|認知症対策で「コスト」と「柔軟性」を徹底比較!
- 投稿:2025年06月11日
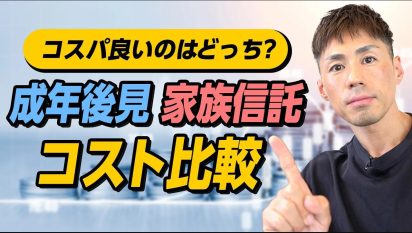
認知症対策として今注目の「成年後見制度」と「家族信託」。どちらも将来に備える仕組みですが、費用面や柔軟性には大きな差があります。今回は、司法書士の視点から、初期費用と継続費用に分けて、両制度を詳しく比較します。
※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!
目次
1. 成年後見制度の仕組みと初期費用
成年後見制度は、判断能力が低下した人を支援するために、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任する公的制度です。成年後見人等は、希望しても必ず親族がなれるわけではなく、財産額や複雑さによって司法書士や弁護士などの専門家が選任されることもあります。
- 実費(印紙代、診断書作成費用など):約1〜3万円
- 専門家依頼(司法書士・弁護士):約10〜30万円
- 鑑定費用:10〜20万円(家庭裁判所による鑑定)
👉 実費だけなら1〜3万円ですが、専門家依頼+鑑定が入ると数十万円になることもあります。
2. 家族信託の概要と初期費用
家族信託は、財産管理や運用の権限を判断能力が低下する前に家族へ託す仕組みです。
- 信託契約書作成:専門家依頼で約20〜50万円ほど(財産額や複雑さで変動)
- 公証人手数料:5〜10万円
- 不動産登記費用:司法書士報酬(5~15万円ほど)+登録免許税(例:1,000万円の不動産で約4万円)
👉 初期費用だけを比較すると、家族信託の方が高額になりがちです。ただ、契約書の内容次第では柔軟な設計が可能です。
3. 継続コスト(ランニングコスト)比較
成年後見制度
後見人が専門家の場合:月額2〜6万円(資産規模による)
例:財産1,000〜5,000万円なら月額3〜4万円、5,000万円超なら5〜6万円
→ 10年間ならトータル360万円〜720万円。
家族信託
家族間完結なら継続費用はほぼゼロ
ただし、信託監督人や専門家の関与が継続的に必要な場合は別途コスト発生の可能性あり。
👉 公的制度で安心感はあるものの、成年後見は長期的なコストが重くのしかかる可能性があります。対して、家族信託は初期費用こそかかるものの、ランニングコストを抑えられる柔軟性が魅力です。
4. 柔軟性とコストパフォーマンスの視点
- 成年後見制度
– 家庭裁判所の監督下で運用自由度は低く、資産運用は禁止される
– 公的な安心感がある反面、制度の硬直性とコスト負担がネックに - 家族信託
– 信託契約で自由度の高い資産運用が可能
– 初期投資は高いが、長期的に見ると費用効率が良いケースが多い
5. まとめ:どちらが向いているの?
| 制度 | 初期費用 | 継続コスト | 柔軟性 | 公的安心感 |
|---|---|---|---|---|
| 成年後見 | 低〜中 | 高 | 低 | 高 |
| 家族信託 | 中〜高 | 低 | 高 | 中 |
- 短期〜中期で、コストを抑えたいなら家族信託
- 公的な監督のもとで安心して保護を受けたいなら成年後見
- もっと自由度と将来的な運用効率も重視したいなら、家族信託が有力な選択肢
最後に
判断能力が低下する前に、将来の選択肢を整理しておくことが重要です。成年後見制度も家族信託も、それぞれにメリット・デメリットがあります。家族構成や財産規模、ご意向に応じた最適な制度選びが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、しっかりとご検討ください。

