[遺言・後見・家族信託]
成年後見制度は“途中でやめられる”時代へ?改正で進む柔軟対応と制度見直し
- 投稿:2025年07月02日
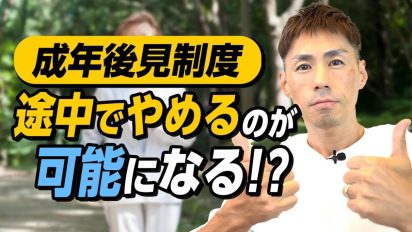
今回は、成年後見制度に関する注目ニュース──「途中で辞められる可能性がある」という大きな改革案について解説いたします。制度の現状と課題、中間試案のポイント、今後のスケジュールまで、詳しくお伝えします。
※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!
目次
成年後見制度の現状と課題
❌ 終身性
現行制度では、一度利用申立てすると原則として「終身性」となっていて、基本的に本人の判断能力が回復しない限り、途中の制度終了は不可能です。特に認知症の場合、後見開始後に判断能力が戻るケースはほぼなく、結果として「死ぬまで続く制度」として捉えられています。
❌ 特定の手続きが進められない
不動産など大きな財産の処分、相続における遺産分割協議など、判断能力が必要となる手続きが本人単独ではできなくなります。そのため、これらの手続きのために成年後見をスポット的に利用したい場合でも、制度の柔軟性がないために一度利用を開始すると途中でやめられず本人や家族にとって望まない結果を生む可能性があります。
❌ 費用と介入の負担
親族以外の人が後見人等になった場合には原則として後見人等への費用が発生します。また、家庭裁判所の介入も続きます。報酬は財産規模に基づいて算定され、後見人が司法書士など専門家の場合、家族にとっても金銭的・心理的負担が重くのしかかる可能性があります。
法制審議会の「中間試案」による主な改革案
2025年6月、法制審議会は成年後見制度の柔軟化に向けた中間試案を公表しました。ここではその主要なポイントをご紹介します。
| 項目 | 現行制度(2025年現在) | 中間試案(法制審議会案) |
| 制度の終了 | 原則として終身利用(本人が死亡するまで終了できない) | 本人の状態改善や不要と判断された場合は、途中終了が可能に |
| 利用期間の設定 | 期間の概念なし(開始=原則一生) | あらかじめ期間を設定 → 更新・終了の判断 |
| 代理権の範囲 | 類型(後見・保佐・補助)により一律に決定 | 本人のニーズに応じて個別に設定可能(例:遺産分割だけなど) |
| 後見人の報酬決定 | 財産額をベースに裁判所が画一的に判断 | 事務の内容や負担に応じて、柔軟に決定 |
| 後見人の選任基準 | 法律上の定めあり、本人の意向反映は限定的 | 本人の意向・生活状況などをより重視して選任・解任を判断 |
| 制度の使いやすさ | 一度始めるとやめられないため、心理的ハードルが高い | 終了もできることから、必要なときだけ使いやすくなる |
| 対象行為の限定 | 一度始めると全財産にわたる包括的代理 | 医療契約や財産処分など、特定の行為に限定して後見可 |
| 本人の自己決定権 | 制限される場面が多い | 本人の意思や自己決定権を尊重した制度設計 |
🔹 終身の枷から脱却
利用期間を事前に定められるため、「いつまで利用したい」といったスポット利用が可能になります。また、必要がなければ更新せず終了することもでき、本人や家族の負担軽減につながります。
🔹 目的別の限定代理
成年後見の現制度では不動産・預金・医療などすべての代理を包括しますが、中間試案では「遺産分割だけ」「病院手続きだけ」など、本人の意志に沿った代理権の付与が可能になります。
🔹 後見人選任の柔軟化
現行制度では司法書士や弁護士など専門家による選任が一般的ですが、中間試案では本人や家族の意向、将来の生活設計が反映される制度設計に改善されます。
🔹 報酬制度の透明化
これまで報酬は財産規模中心の計算式でしたが、今後は事務量や手続きの内容に応じた柔軟な報酬設定が求められるようになります。
なぜ今、変わる必要があるのか?
- 社会背景の変化:認知症高齢者の増加により、制度利用者が拡大する中、柔軟な支援の必要性が高まっています。
- 家族の安心:従来は「お金も手間もかかる」制度でしたが、今後は必要なときだけ利用でき、精神的・制度的なバリアが下がります。
- 多様な選択肢の実現:家族信託制度など、成年後見外の選択肢も増えていますが、制度自体にも柔軟性と使いやすさが求められています。
4. 今後のスケジュールと展望
- 意見募集(パブコメ)
—2025年中旬以降、制度を支える具体案について国民の意見を募集。 - 要綱案の策定・法案化
—2025年度内に制度改正の具体内容をまとめ、2026年通常国会に改正民法案として提出予定。 - 成立&施行
—2026年の国会承認後、公布・施行に向けた準備が進みます。
制度改善の恩恵と注意点
✅ 利点
- 部分的な制度利用が可能に:必要な手続きだけを対象にした成年後見の併用が可能になります。
- 後見人への過剰介入の防止:不要な支援を省くことで財産管理や医療判断も本人に寄せやすくなります。
- 報酬・選任の透明性強化:家族にも理解しやすい制度設計が進みます。
⚠ 注意点
- 柔軟性が高まる一方で、更新判断や代理権範囲のトラブル防止には、適切な説明と理解が必要です。
- 家族信託や任意後見と併用する場合でも、それぞれの制度の特性を正しく把握しておくことが重要です。
まとめ:利用しやすさが劇的に改善へ!
今回の法制審議会中間試案は、従来の「終わることのない」成年後見制度から、利用者・家族の意志を尊重した柔軟設計への転換を目指すものです。
- 「何年だけ使いたい」に応える期間設定。
- 「医療契約だけ」「遺産分割だけ」などの代理限定。
- 本人・家族の意志が反映される後見人選任。
- 財産だけでなく作業量に応じた報酬基準の導入。
これらの変化は、家族や本人にとって安心して使える制度への一歩。今後は正式な法案としてまとめられ、改正実現へと進む見込みです。
当事務所でも、この流れを踏まえて家族信託や任意後見などの提案を行っています。今後、最新情報が公表されましたら、改めてご案内いたします。

