[遺言・後見・家族信託]
家族信託を“悪用”するケースとは?財産隠しの実態と回避するための4つのポイント
- 投稿:2025年07月07日
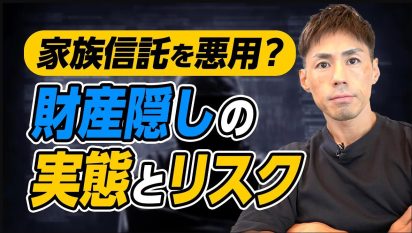
当事務所のYouTubeやホームページでは家族信託の本来の意義やメリットを日頃からご紹介しております。しかし、最近ニュースで報じられた“家族信託による財産隠し”事案には、深刻なリスクが伴います。今回は、ヤフーニュースや毎日新聞で取り上げられた「暴力団トップによる土地名義変更」事件をきっかけに、家族信託の悪用リスクと、その回避策について詳しく解説します。
※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!
目次
家族信託の“悪用”ケースとは?
■ ニュース事例の概要
先日報じられた毎日新聞の報道によれば、特定危険指定暴力団「工藤会」のトップである野村被告が自身所有の土地23筆と自宅を、親族を受託者(信託の財産管理者)とする信託契約によって名義変更し、債権者による差し押さえを回避しようとした疑いが報じられました。形式上は親族名義に移転されたものの、実質的には野村被告が委託者かつ受益者であったため、名義変更後も財産の支配・利益取得が可能な実質上の所有者でした。
■ 「信託財産」とは?
信託契約が成立すると、その財産は「信託法」に基づく信託財産となり、委託者個人の所有財産ではなくなります。これにより、債権者による差し押さえの対象から外れる可能性が高まります。実務上、強制執行をかけるには、手続きが格段に複雑・困難化することになります。
■ 受益権への差し押さえは可能だが…
信託後の受益者(この場合は野村被告)は「受益権」を持ちます。この受益権は財産的価値のある債権(不動産の実質的な所有権)のため差し押さえ可能です。しかし、実物不動産ではないため、実質的な回収までは時間と手間が必要です。
家族信託が悪用されるリスク
- 名義変更による差し押さえ回避
債権者は信託された不動産を、その名義人(受託者)から差し押さえられず、強制執行まで至りにくくなります。 - 手続きの複雑化・困難化による実質的な財産保全
受益権への差し押さえを経ても、不動産の実質価値に換えて取り崩すまでに時間がかかるため、債権者にとって不利になります。 - 信託契約の取消リスク
信託契約が「詐害行為」(債権者を害する行為)と判断されれば、契約そのものを取り消すことができる可能性があります。しかし、契約の詐害性を債権者側が立証しなければならず、これもハードルが高いです。
正しく使うための4つのポイント
本来、家族信託は「認知症対策」や「円滑な相続準備」に有効なツールです。悪用を防ぐため、以下の4つは必ず押さえておきましょう:
- 目的を明確にする
認知症対策・財産承継・相続円滑化を目的とし、「債権者回避」が主目的にならないよう注意。 - 信託契約の内容を慎重に設計する
誰を受託者にするのか、どの財産を信託するのか、信託の終了条件や残余財産の取り扱いを明示し、目的に沿った設計を。 - 専門家に相談する
司法書士・弁護士・税理士などによる多角的なチェックが重要です。 - 受益権・残余財産の後処理に注意
信託終了時や課税時、残余財産をどう処理するか。税務面や登記手続きなども含め適切に整備しておく必要があります。
まとめ
家族信託は「安心できる未来設計のツール」です。しかし、悪用されると「財産隠し」に使われたり、その疑いを持たれる恐れがあります。正しく設計・運用するためには、
- 目的の明確化
- 契約内容の慎重設計
- 専門家のサポート
- 信託終了後の処理対応
が不可欠です。ご自身とご家族の安心の未来のため、信頼できる専門家とともに家族信託を適切にご活用ください。

