[相続]
「相続放棄したのに借金の請求が来た…支払い義務はあるの? 司法書士が教える対処法と誤解しやすいポイント」
- 投稿:2025年08月13日
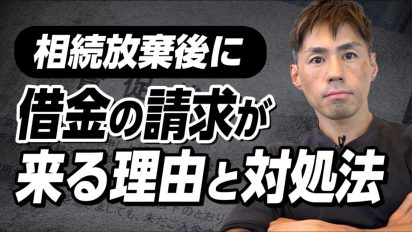
今回は、非常に相談が多く、みなさんが直面しやすいトラブルの一つ「相続放棄(そうぞくほうき)をしたのに、なぜか借金(債権)の請求が来てしまった…支払わなきゃいけないの?」という問題について、司法書士の立場から詳しく解説いたします。
※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!
目次
相続放棄とは?
まず基本的な前提として、「相続放棄」とは、故人(亡くなった方)の債権・債務(プラスの財産もマイナスの財産も含めて)を一切相続しないという法的手続きです。この手続きには、家庭裁判所への正式な申述書(相続放棄の申述書)提出が必要で、受理されることで「初めから相続人ではなかった」ことになります。
つまりこの手続きが正しく完了していれば、借金の返済義務は一切なくなります。
なぜ借金の請求が来るのか?主な3つの理由
相続放棄したのに借金の請求が来た場合、主に次の3つの理由が考えられます。
(1)債権者が「相続放棄」した事実を知らない
家庭裁判所が「相続放棄が成立しました」と認めても、それが債権者(消費者金融やカード会社など)に自動で伝わることはありません。そのため、債権回収のために相続人を調べ、相続放棄した方にも請求が及ぶことがあります。
(2)手続きや書類に不備がある
- 提出先の家庭裁判所が誤っていた
- 書類に不備があったり却下された
- 申述期限(相続の開始・死亡を知ってから3か月以内)を過ぎていた
こうした場合、放棄したつもりでも法的には「相続放棄が成立していない」と判断され、請求が来るケースがあります。
(3)次順位の相続人に請求が及んでいる
相続放棄をした場合、例えば子が放棄すると、次に「直系尊属」→「兄弟姉妹」という順で相続順位が移ります。そのため、自分は放棄したから安心…と思っていても、次の順位の方に請求が来る可能性があり、その連絡が間違って届くこともあります。
請求が来たらどうすればいい?正しい対処ステップ
万が一、相続放棄後に債権者から請求が来た場合、以下の対応を心がけてください。
- 家庭裁判所発行の「相続放棄受理通知書」を確認する
この書類があれば、相続放棄が正式に認められた証拠になります。これを手元で確認してください。 - 債権者へ“文書で”通知する
「相続放棄をした」旨を伝え、相続放棄申述受理通知書のコピー等を送るのがベストです。 - 不安な場合は司法書士や弁護士に相談する
書類が見つからない、債権者が執拗に連絡してくるなどの場合は、すぐに専門家に相談し、対処法を検討しましょう。
相続放棄に関する誤解と注意点
よくある誤解や注意点も押さえておきましょう。
- 書類を「出せば安心」というのはNG
家庭裁判所に書類を提出しただけでは済みません。申述が「受理」されて初めて法的効力を持ちます。 - 自治体では受け付けてもらえない
役所(市区町村)では相続放棄の手続きはできず、必ず管轄の家庭裁判所へ申し出る必要があります。 - 基本的に“財産処分”は避けるべき
相続放棄を予定している場合、遺産の処分(売却や譲渡など財産価値があるものの処分)は「みなし単純承認」となり、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。価値のない財産の整理や形見分けなどは問題ありませんが、不安な場合は専門家に相談を。
まとめ:覚えておいてほしいポイント
- 相続放棄したのに請求が来ても、「ちゃんと成立していなかった」わけではないことが多い。
- まずは「相続放棄申述受理通知書」の有無を確認し、債権者に文書で通知して対応しましょう。
- 不安な場合は遠慮なく専門家に相談することが、トラブルを避ける最短ルートです。
借金を相続しないために非常に有効な制度である「相続放棄」も、使い方や理解の仕方を誤ると逆に不要な負担を背負いかねません。正しく、かつ冷静に対応することが何より大切です。相続放棄を考えている方、または既に行ったけれど不安がある方は、ぜひ専門家へのご相談を検討してください。

